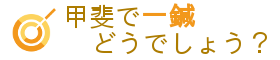「儒教のかたち こころの鑑」展に行ってきました!
少し前の話ですが、サントリー美術館で行われた「儒教のかたち こころの鑑」展に行ってきました。
そもそも儒教ってご存じでしょうか?
僕にとっては鍼灸師になるまで「中学か高校で習ったかも?」くらいのものでした。
しかし、儒教って東洋医学には密接な関係があるんです。
儒教は東アジア文化の基盤
儒教は約2500年前の紀元前6世紀頃、中国で孔子という人物によって創始されました。
古代の聖人に近づくための作法や心構えを説く教えです。
中国だけではなく、日本を含む東アジアの国々の文化や価値観に大きな影響を与えました。
例えば、礼儀や仁義も儒教に由来する考え方なんです。
気の哲学は儒学の教典に!
そんな儒教を探究した儒学という学問があります。
儒学の教典(このブログでもたまに出てくる『易経』もその一部です)では、気の哲学を使って森羅万象を解釈します。
つまり全ての現象は気の働きで成り立っていると考えるのです。
儒学の教典は中国での役人採用試験にも使われていたので、やはり中国文化を語る上で避けることはできません。
この前提があっての東洋医学なので、鍼灸師としては儒教文化に触れる機会を見逃せなかったわけです。
日本人も儒教・儒学を振り返るべし
日本での儒学も、江戸時代には幕府が公的な学問所を作ったり、民間でも寺子屋で教えられていたり、とても馴染みが深いものでした。
明治維新以降の西洋化で様変わりはしましたが、今でも『論語』が本屋に並んでいるのを見かけますよね。
それに甲斐市民ならご存じの山縣大弐も儒学者なので、ちょっと親近感が湧くのではないでしょうか?
今回の展示は、東洋医学に直接つながるものこそ多くはありませんでしたが、日本との関係を改めて知った良い機会でした。
展示自体は終わってしまいましたが、図録が待合室あるので興味がある方はお手にとって観てみてください!