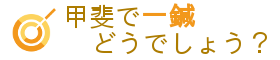東洋医学的な身体の診方は?
前回は健康診断の検査結果について書きました。
[関連記事:東洋医学的な検査結果活用法!]
当然ですが、健康診断は西洋医学の考えの基で行われます。
では東洋医学ではどうやって身体の状態を把握するか、今回はそちらを紹介しようと思います。
東洋医学の見方は4つ!
東洋医学で身体の状態を知る方法は、伝統的に四診と呼ばれています。
「視る」、「聞く」、「問う」、「触る」、で4つですね。
前回書いた日常生活の振り返りは「問う」ですし、当院で重視するお腹やツボを診ることは「触る」にあたります。
「視る」は目から得られる患者さんの情報全般ですが、「聞く」は耳だけじゃなく鼻も使うのが面白いところです。
使う道具(鍼灸や漢方)ややり方(理論や流派)によって差異はあれど、ほぼ全ての東洋医学家は何かしらの四診を使っているはずです。
四診で何がわかる?
当院で四診で「触って」いると、患者さんから「そこのツボが押して痛いのは何ですか?」なんて質問をもらいます。
四診では、流派によって気や血や水の流れや偏りと色々な表現が使われますが、共通してるのは全身のバランスを診ています。
その情報を活用して病の状態を把握したり、身体の傾向に合わせた治療をしたりするんです。
ちなみに当院で行ってる積聚治療では、偏りの過多から疲れ具合を判断もしています。
四診を使って施術をグレードアップ!
東洋医学的な診方をザッと書いてみました。
東洋医学の歴史も二千年と長いので、一言ではとても言い表せないほど多岐に枝分かれしています。
逆に言えば、だからこそ色んな視点で身体を診る手法が磨かれてきました。
また、四診ではセンサーなどを使わないため、診る側の技術の個人差も大きく出ます。
僕も技術を磨き続けてきて、たまに患者さんが言っていない体調もわかるようになってきましたが、師匠はもっともっと精細に診て相手の身体を緻密に把握しています。
情報があればあるほど患者さんのその時に合わせたツボや刺激量を選べるので、より効果的に施術を行えるようになります。
だからこそ、僕も東洋医学家の一人として、四診を更に使いこなせるように頑張ります!